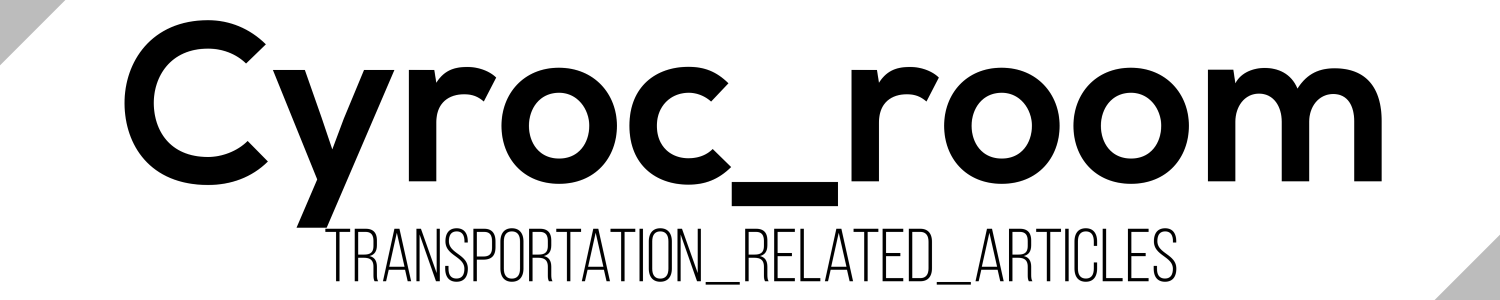首都圏から東北、甲信越にかけて長い路線網を有するJR東日本は4月30日に2024年度設備投資計画を発表しました。
(これは2024年5月13日に既に公開されている記事です。)
インフラ投資
安全対策のために引き続きの「大規模地震対策」、「踏切事故対策」、「運転保安装置整備拡大」の三つが示されました。
大規模地震対策


JR東日本は阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災からの教訓、そして将来発生するであろうとされている首都直下地震への対策として鉄道施設や盛り土等に対して補強を加えてきました。 なかでも東日本大震災や首都直下地震を踏まえた対策として2012年から約3,400億円規模の補強工事が行われており、2024年3月末に計画通り終了しています。 2017年からは首都直下地震の最新情報や新たな活断層を踏まえ、対策範囲を拡大した3,000億円規模の地震対策を行い、2028年度の完了を目指して引き続き対策を進めています。
しかし、2021年、22年と福島県沖を震源とする最大震度6以上の大地震が2度発生し、22年の地震では走行中だった東北新幹線の列車が地震の影響で脱線、復旧に2ヶ月を要しました。 被害は車両のみにとどまらず、橋脚の損傷や沈み込み、電柱の損傷等甚大な被害が発生したためJR東日本は新幹線設備への対策計画を見直し、3,000億円規模から4,500億円規模へと計画を拡大しました。 高架橋の橋脚や電柱に対して補強を行う他、補強時期自体の前倒しが行われました。
22年の地震で比較的大きな被害が発生した橋脚はラーメン橋台と呼ばれ、一般の橋脚と比較すると必要な本数が少ないことがメリットです。しかし1本がより重いというデメリットから、柱の下部が地震の負荷に耐え切れず潰れてしまい高架橋の沈み込みが発生しました。そのためJR東日本は橋脚の中でもラーメン橋脚を優先して補強を行い、2028年度までに全6,000本の補強を目指します。 平行して普通の高架橋脚を補強。21年度から続けている電柱の補強は拡大。33年までに普通高架橋脚13,200本、電柱8,000本の施工を目指すとしています。
2021年発表の資料では被災した場合に輸送障害が発生する重要設備である電気設備や車両センター、変電所等も追加して設備対策を行っていくとしています。
踏切事故対策


JR東日本は2020年に発表した資料で「踏切事故対策の基本は踏切をなくすことであり、地域の皆さまのご協力をいただきながら踏切廃止に向けた取組みを進めています。」 (JR東日本プレスリリース ”より安全な駅ホーム・踏切の実現に向けた取組みについて”)としているように事故対策として踏切の跨線橋化や路線の立体交差化を行っています。 南武線の矢向駅~武蔵小杉駅で行われる予定の立体交差化では9箇所の踏切が無くなるとされていて事故対策のみでなく交通の円滑化にも貢献するとされています。
第3種踏切、第4種踏切と呼ばれる簡素な構造の踏切については、閉鎖が困難な場合は遮断機や警報機が備え付けられている第1種踏切へのアップグレードを行っていくとしています。
運転保安装置整備拡大


JR東日本は現在仙石線や埼京線で運用されている列車制御システムである”ATACS”を山手線全線、京浜東北線の大宮~東神奈川間への導入を予定しています。 従来の保安装置ではレールに電流を流すことで列車がどこにいるのかを検知(軌道回路)していましたが、ATACSでは列車自体から走行位置を検知し、無線通信で列車を制御します。 この方式では従来必要だった信号機や軌道回路が不要になり、列車の速度計に付いている車内信号機によって列車に速度の指示を行います。 無線による情報を基に制御を行うため、データを入力することでいままで運転士の操作に頼っていた徐行信号機や駅、踏切での非常停止ボタン対応等をシステムによる制御下とでき、 自動で減速、停止を行うことができるようになります。
また列車の現在地、速度と踏切までの距離、列車の性能等から計算によって踏切を無線で制御します。従来、踏切の制御は基本的には固定の場所を通過したら踏切を動作させるという ものでしたが、遅延や事故などで通常より遅い速度で走行している場合、必要以上に踏切の動作が長時間になり渋滞の原因となることがありました。 この方式であれば速度や位置から踏切を適切な時間で動作させることができ、通行の円滑化が期待できます。
ローカル線区向けには”GNSS無線踏切制御システム”を開発中であり、人工衛星より列車の位置を特定し、携帯回線を利用して踏切の動作と列車の速度を制御します。 このシステムではいままで必要としていた踏切設備の一部が不要となり、メンテナンスの簡略化が行えるようになります。今後八高線に導入を予定しているとしています。
東北・上越新幹線では2030年度での自動運転化に向けて自動運転装置の開発を進めており、自動運転も考慮した上で新白河~盛岡間での信号装置取替を行っています。
ホームドア設置

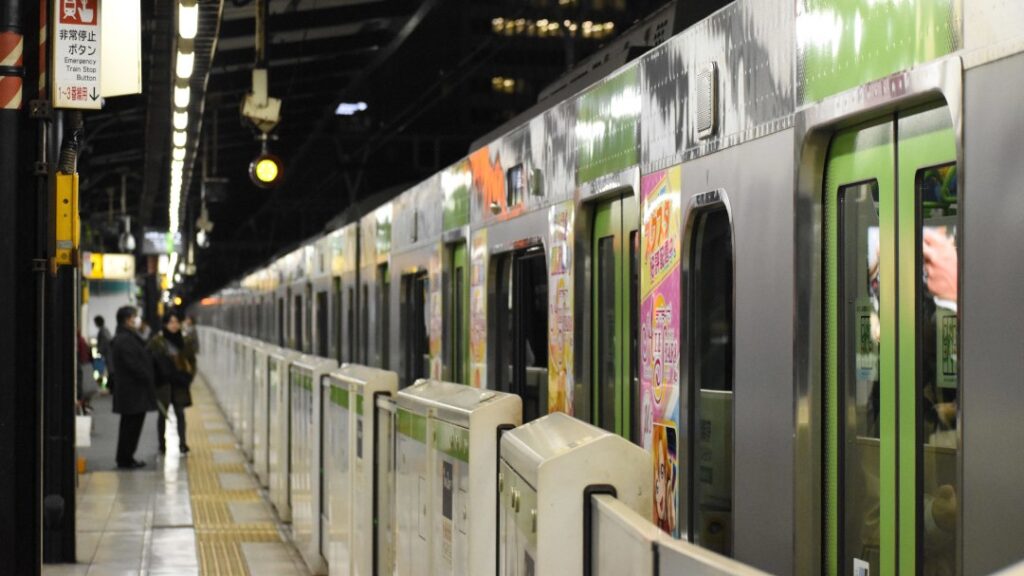
度々発生する人身事故や乗客転落事故のために鉄道各社は一つの対策としてホームドアを設置しています。JR東日本は31年度末までに東京圏330駅にホームドアを設置 する計画で、24年度は12駅にホームドアを設置するとしています。設置予定の駅は以下の通りです。
- 京浜東北線: 鶯谷
- 常磐線各駅停車: 我孫子 松戸
- 中央総武線: 新小岩 本八幡
- 南武線: 川崎 武蔵溝ノ口 津田山 久地 宿河原 稲田堤 西府
JR東日本によると”昨今の半導体不足により材料調達に遅れが発生しているが、当初の計画通り31年度末での完了を目指す”としています。
事業用車の増備
JR東日本は2021年から今まで運用していた古い機関車を新型車両に置き換えています。


1枚目の写真 “EF64 1030(2021年2月 北上尾駅 – 上尾駅間)MaedaAkihiko – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる”を改変して作成
2枚目の写真 量産車の02編成MaedaAkihiko – 投稿者自身による著作物, CC0, リンクによる
JR東日本では今まで車両の回送等に古い電気機関車を運用しており、車両の維持・メンテナンスの他、運転方法が一般の電車とは異なる為にある程度の習熟が必要となり かなりの手間が掛かっていました。導入した新型電車では車両の構造を通勤電車と共通化することでメンテナンスだけでなく運転も通勤電車と同じようにすることができ 機関車のような難しい操縦に習熟する必要がなくなりました。


1枚目の写真 “ホッパ車を牽引するDE10 1076(2017年5月18日)This photo was taken with Olympus E-M1 Mark II – 工9585レ DE10 1076, CC 表示-継承 2.0, リンクによる”を改変して作成
2枚目の写真 走行するGV-E197系いけたま電鉄 – 投稿者自身による著作物, CC0, リンクによる
新型の電車は2両編成を組む電車のE493系(右一番上写真)と1両単位の電気式気動車GV-E197系(右上)の2種類で、これらがJR東日本の所有する国鉄から継承した電気機関車、ディーゼル機関車のいくつかを置き換える予定です。 GV-E197系はディーゼル機関で発電し、その電気を利用して電車のように走るので気動車より構造が簡単で保守性が向上しました。
GV-E197系はGV-E196形という車両を含み、GV-E196形は線路の下の石であるバラストを輸送、散布する為のホッパ車と呼ばれる車両で、国鉄から継承したホッパ車(左上の黒い貨車)を置き換えます。
いままでのディーゼル機関車を利用した列車(左上)では折り返すときに機関車を前から一番後ろに連結し直し折り返す必要がありましたが、新型車両では2両の車両で挟みこむように運用することで 普通の電車と同じように運転士が移動するだけで折り返すことができ、連結する際の人員や手間等が不要になり効率的に運用出来るようになりました。

“GV-E196形 MaedaAkihiko – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる”を改変して作成
変電所更新
JR東日本は変電所更新について計画的に実施し、安全性と効率を向上させるとしています。
またJR東日本は日立製作所と共同で新しい変電所システムの開発を行い、2025年度に導入するとしています。いままで敷設されていた多数のケーブルを1本の光ケーブルに統合することで いままで困難だった2重系統化が可能になり、一方の系統が故障した場合にも変電所の運用を続けることが出来るようになります。また9割のケーブルを省略でき、スペースや工事を省略 できるようになります。JR東日本は24年度に機器を搬入、25年度に22,000Vでの運用、26年度に22,000V運用終了、27年度に66,000Vでの運用開始を予定、小岩変電所に導入される予定です。
架線設備更新


従来部品点数が多い為に保守性が低かった架線設備に対して、JR東日本は高圧ケーブルを線路脇に通す等して線の本数を減らし、保守性を高めています。 首都圏を中心に延長1,200kmの工事に着手しています。